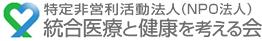Menu
肝細胞がん
【1】肝細胞がんとは
肝臓は、成人で800~1,200gと体内最大の臓器で、ここには多種類の悪性腫瘍が生じます。 この悪性腫瘍は、原発性肝がん(肝臓から発生したがん)と転移性肝がん(他臓器のがんが肝臓に転移したがん)に大別されます。原発性肝がんは、肝細胞がんと胆管細胞がんが95%を占め、残りの5%には、小児の肝がんである肝細胞芽腫、成人での肝細胞・胆管細胞混合がん、未分化がん、胆管嚢胞腺(たんかんのうほうせん)がん、カルチノイド腫瘍などのごくまれながんが含まれます。
年齢別にみた肝臓がんの罹患(りかん)率は、男性では45歳から増加し始め、70歳代に横ばいとなり、女性では55歳から増加し始めます。年齢別にみた死亡率も同様な傾向にあります。
日本国内の死亡率の年次推移は、男女とも最近減少傾向にあり、罹患率は男性で減少、女性で横ばい傾向にあります。死亡率の国内の地域比較では、東日本より西日本のほうが高い傾向にあります。 国内の成人では、肝臓がんの大部分(90%)は肝細胞がんです。よって、本頁では、この肝細胞がん(以下、肝がん)について説明します。
【2】肝がんと肝炎ウイルス
肝がんは、肺がんや子宮頸がんと並び、主要な発生要因が明らかになっているがんの1つです。 最も重要なのは、肝炎ウイルスの持続感染です。ウイルスの持続感染によって、肝細胞で長期にわたって炎症と再生がくり返されるうちに、遺伝子の突然変異が積み重なり、肝がんへの進展に重要な役割を果たしていると考えられています。肝炎ウイルスにはA、B、C、D、Eなどさまざまな肝炎ウイルスが存在しています。肝がんと関係があるのは主にB、Cの2種類です。
肝がんは、B型、C型肝炎ウイルスが正常肝細胞に作用して突然変異を起こさせて発生するものと推定されています。したがって、B型、C型肝炎ウイルスに感染した人は、肝がんになりやすい「肝がんの高危険群」と言われています。
肝炎ウイルスに感染すると多くは「肝炎」という病気になります。その症状としては、全身倦怠(けんたい)感、食欲不振、尿の濃染(尿の色が紅茶のように濃くなる)、さらには黄疸などがあります。しかし、自覚的には何の兆候もなく、自然に治癒することもあります。また、肝炎ウイルスが身体に侵入しても、「肝炎」という病気にならず、健康な人体と共存共栄するという状況もあります。このように、体内に肝炎ウイルスを持っていても健康な人のことを肝炎の「キャリア」といいます。肝炎ウイルスの感染経路としては次のようなものがあります。
1.妊娠・分娩による感染
妊娠・分娩を介して「肝炎ウイルスを持った母親」から子供へという感染経路があり、これを垂直感染といいます。この垂直感染は、主にB型肝炎に多く認められ、同一家族・家系に何人もの肝炎ウイルス感染者が存在することがあり、これを肝炎の「家族集積」といいます。現在では、妊娠中の母親は血液検査で肝炎ウイルスの有無が必ず調べられます。母親がB型ウイルスの保菌者と判明すると、垂直感染を防止するために、新生児には直ちにワクチン治療が行われ、B型肝炎の発病を防止する措置がとられています。
2.血液製剤の注射による感染
肝炎ウイルスを含んだ血液の輸血を受けると、輸血を受けた人の身体に肝炎ウイルスが侵入してしまいます。輸血が必要な場合は、病気・けがなどで身体の抵抗力が低下していることが多く、肝炎が高率に発症します。現在は、輸血に用いる血液はすべて厳重な品質管理が行われており、特にB型、C型についてはウイルスの有無を検査して、ウイルスの存在する血液は輸血には使わないという体制が確立しています。そのため、現在では輸血による肝炎は激減しています。ただし、B型にもC型にも検査で見つけられない場合が、わずかながらあることも事実で、輸血による肝炎が完全にゼロになったわけではありません。
3.性行為による感染
性行為もウイルス感染の経路となる可能性があります。しかし、B型肝炎やC型肝炎の夫婦間感染率は低く、通常の性行為では感染する危険性は低いことが報告されています。ただし、B型肝炎にはHBe抗原が陽性の場合は感染力が強いので、医師に相談することをお勧めします。
以上、1.~3.の感染ルートのどれにも思いあたるものがないという場合も多く、「このルートだ」と断定することは必ずしも容易ではありません。 1.~3.以外の未知の感染ルートがあるかもしれません。 肝炎ウイルスの感染は個人の意識・知識によりある程度予防できますが、防止できない部分があることも事実です。肝炎ウイルスに感染してしまったら、即、肝がんになり、生命が脅かされるわけではありませんが、「肝がんの高危険群」と考えて対処すべきです。
肝炎ウイルスに感染していることが判明するのは、
- 身体に変調をきたし、受診して診断される
- 健康診断の血液検査で発見される
- 献血をした際に血液が輸血に適するか否かの検査で後日連絡を受ける
- 他の病気で受診して手術や検査を受ける必要が生じた際の血液検査で判明する
などの場合があります。また、家族の一員が肝炎ウイルスに感染していることが判明すると、医師は「家族集積」性を考慮して、ご家族の血液検査も勧めます。
肝炎ウイルスに感染していることが判明したら、次には「キャリア」であるのか「肝炎」という病気になっているのかを調べる血液検査が必要です。しかし、ともに肝がんにかかりやすい候補者と心得るべきで、「肝がんの高危険群」といえます。
高危険群の人に肝がんを発生させないような予防法についても、研究が進んでいる途上で、現段階では、C型肝炎に対して期待されている治療はインターフェロンによる治療です。インターフェロン治療により発癌のリスクを軽減できたとの報告も幾つかあります。 また、最近ではペグインターフェロンという新しいインターフェロンやリバビリンというインターフェロンの効果を高める内服薬も登場し、従来よりも治療効果が高まっており期待されています。また、B型肝炎に関しては、内服の抗ウイルス薬であるラミブジンが発癌までの期間や肝硬変への進展を抑制したとの報告もあります。しかし、いずれもまだ十分な決め手となっていないのが現状です。ですから、高危険群者は肝がんにかかっても手遅れにならないうちに早期発見・治療することが必要です。
【3】症状
肝がんに特有の症状は少なく、肝炎・肝硬変などによる肝臓の障害としての症状が主なものです。国内の肝がんは、肝炎ウイルスの感染にはじまることが大部分で、肝炎・肝硬変と同時に存在することが普通です。肝炎・肝硬変のために医師の診察を受ける機会があり、肝がんが発見されるというケースが多くみられます。
肝炎・肝硬変の症状といえば、食欲不振、全身倦怠感、腹部膨満感、便秘・下痢など便通異常、尿の濃染、黄疸、吐下血、突然の腹痛、貧血症状(めまい・冷や汗・脱力感・頻脈など)が挙げられます。肝がんの症状といえば、肝臓の部位に「しこり」や痛みを感ずることです。また、突然の腹痛、貧血症状は、肝がんが破裂・出血したときに認められる症状です。しかし、これらの症状は、他の臓器の病気でもみられますので肝がんに特有とはいえません。また、肝がんから、このような症状が出現した場合は、かなり進行した段階といわざるを得ません。
【4】診断
肝がんの診断は、血液検査と画像診断法により行われます。どちらか一方だけでは不十分です。また、血液検査や画像診断法を駆使しても「肝がん」と診断がつけられないこともあり、その場合は針生検といって、肝臓の腫瘍部分に針を刺して少量の組織片をとり、顕微鏡で調べることも行われます。
1.画像診断
肝がんの診断に重要な検査は、超音波検査とCTです。ともに痛みや苦痛がほとんどなく、外来で行える検査です。超音波検査は放射線の被曝がなく、腫瘍と血管の位置がよくわかります。ただ、患者さんの状態や部位によっては見えにくい場合があります。 CTは身体の横断面を撮影します。肝がんは血管の豊富な腫瘍で、造影剤(ぞうえいざい)という薬を静脈から急速に注射して、早いタイミングで撮影すると肝がんがよく描出されます。
正確な個数の確認が必要な場合には血管造影をしながらCTを撮影することもあります。これをアンギオCTといい、個数の確認には最も有用です。
MRI検査は、超音波検査やCTで肝がんがあることがわかれば、診断や治療において必須な検査ではありません。しかし、典型的な肝がんではなく、超音波検査やCTで診断が困難である場合は、いろいろ条件をかえてMRIを撮像することで、より診断が深められることがあります。
2.腫瘍マーカー
肝がんの腫瘍マーカーとしては、AFP(アルファ型胎児性タンパク)やPIVKA II(ピブカ-ツー)などが用いられます。一般的に腫瘍マーカーは、がんが存在すると陽性となり、がんが大きくなるにつれて、腫瘍マーカーも数値が上昇します。治療をしてがんが小さくなったり、身体から完全になくなってしまえば、腫瘍マーカーの数値は下降したり、正常化(陰性になる)します。
このように、腫瘍マーカーは、がんの診断や治療の効果判定、再発の有無の診断に役立ちます。肝がんの腫瘍マーカーは、肝がんであっても陰性のことがあり、また、肝がん以外の肝炎・肝硬変だけでも陽性のことがあり、全面的に信頼できるわけではありません。したがって、腫瘍マーカーの検査だけでは不十分で、どうしても画像診断を同時に行わなければなりません。
3.針生検
画像診断や血液検査の結果から、多くの場合は肝がんと診断がつけられます。しかし、中には典型的な結果が得られず診断がつけられないことがあります。このような場合には、超音波検査で肝臓内部を見ながら細い針を腫瘍部分に刺し、少量の腫瘍組織を採取する針生検という方法を行うことがあります。ただし、出血を起こしたり、がんを広げてしまったりする危険性がないわけではありませんので、必要性をよく検討してから行うことになります。
4.肝がん検査の頻度
自覚症状が出現してから病院を訪れるのでは手遅れのことが多いため、肝がんの高危険群に属する人は日ごろからの定期検査が必要です。定期検診の間隔は、「肝炎ウイルスに感染している」だけで他に異常がなければ6ヵ月に1回で採血や超音波検査などを行います。肝炎ウイルスの感染に加えて、肝機能に異常がある時は3~4ヵ月に1回、採血や超音波検査などを行い、必要に応じてCT検査などを行います。腫瘍マーカーが上昇している場合には、さらに頻繁に検査することがあります。
【5】病期(ステージ)
がんの進行程度(病期)を大まかに示すものとして「ステージ分類」があります。 ステージ分類は1から4までの4段階に分けられており、数字が大きいほどがんが進行していることを意味します(日本肝癌研究会の定めた「原発性肝癌取扱い規約(第4版)」から抜粋)。
肝がんが、(1)直径2cm以下である、(2)1個だけである、(3)血管侵襲(がんが血管の中に入り込んでいる状態)がない、という条件で
-
ステージ1
(1)(2)(3)のすべてに合致
-
ステージ2
(1)(2)(3)の2項目に合致
-
ステージ3
(1)(2)(3)の1項目のみに合致
-
ステージ4
(1)(2)(3)の1項目も合致しない、もしくはリンパ節転移がある、遠隔転移(肝臓以外の身体部分に転移)がある
また、肝機能のよし悪しを分類するのが「肝障害度」分類です。「肝障害度」は、A、B、Cの3段階に分けられます。AからCの順序で肝障害の程度が強いことをあらわします。 本来は細かな数字で規定されていますが、およそ次のような状態に相当します。
- A. 肝臓障害の自覚症状がない
- B. 症状をたまに自覚する
- C. いつも症状がある
【6】治療
外科療法、穿刺療法(ここでは経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法など、身体の外から針を刺して行う治療を一括して穿刺療法としてまとめます)、肝動脈塞栓術の3療法が中心です。この他に、放射線療法や化学療法(抗がん剤投与)などがあります。 肝切除、肝動脈塞栓術、穿刺療法は、それぞれ長所・短所があり、一概に優劣をつけることはできません。がんの進み具合、肝機能の状況などの条件を十分考慮した上で選択されます。
1.外科療法
-
(1)肝切除
がんを含めて肝臓の一部を切除する治療法で、最も確実な治療法のひとつです。最近では腹腔鏡による肝切除も徐々に行われつつありますが、適応は限定されており、一般には比較的大きな皮膚切開を必要とします。術後の入院期間はおおよそ2週間で、合併症としては出血、胆汁漏、肝不全などが挙げられます。
-
(2)肝移植
日本では、脳死肝移植は法的には認められていますが、提供者の不足などの問題によって、実際にはほとんど行われていません。その代わり、主に近親者から肝臓の一部を提供してもらい、肝臓を移植する生体肝移植が大学病院を中心に行われています。肝移植の年齢制限は65歳以下とするところが多く、肝機能の面では肝硬変のために肝切除などの局所治療が困難な場合に、治療法のオプションとして考えられます。
2.穿刺療法
-
(1)経皮的エタノール注入療法
経皮的エタノール注入療法とは、無水エタノール、すなわち純アルコールを肝がんの部分へ注射して、アルコールの化学作用によりがん組織を死滅させる治療法です。超音波検査でがんの正確な場所にねらいをつけて針を刺し、エタノールを注入します。したがって、超音波でよく見えない場合は、エタノールの注入が安全かつ十分にできないこともあります。 がんの大きさ・数などの制限があることやがんの一部が残ってしまう危険性があるという欠点はありますが、比較的手軽に行うことができ、身体に与える副作用が少なく、短期間で社会復帰できるという利点があります。
-
(2)ラジオ波焼灼療法
特殊な針を体外から肝がんへ挿し込み、通電することにより、その針の先端部分から熱が発生し、がんを焼灼する治療法です。通常は、超音波をガイドに行いますが、CTや腹腔鏡などを用いて行うこともあります。これらの治療法もエタノール注入療法と同様に、がんの大きさは3cmより小さく、がんの個数は3個以下の小型肝がんが対象となります。
3.肝動脈塞栓術
肝動脈塞栓術とは、がんに酸素を供給している血管を人工的にふさぎ、がんを兵糧攻めにする治療法です。大腿部(ふともも)のつけ根の部分にある大腿動脈からカテーテルを挿し込み、先端を肝動脈へ進めます。このカテーテルを通じて、1mm角大に細かくしたゼラチン・スポンジなどを注入し、肝動脈を詰まらせて、がんに供給する血流を遮断し、がんを死滅させます。 通常、治療効果を高めるために、抗がん剤と肝がんに取り込まれやすいリピオドールという造影剤を懸濁して、ゼラチン・スポンジを注入する前に投与します。この治療法は、がんが肝臓の内部にとどまっている限りは、解剖学的条件による制限をあまり受けません。 また、肝機能の制限も比較的緩く、黄疸・腹水などがなければ施行可能です。1回の治療に要する入院期間は1週間程度と短く、副作用としては腹痛・吐き気・食欲不振・発熱などがありますが、通常は2、3日でおさまります。ただし、完全に治ってしまう確率はあまり高くありませんので、繰り返し行ってがんを抑え込んでいくという形になります。
4.その他の治療
放射線療法は、骨に転移した時などに疼痛緩和を目的として行われることがあります。また、最近では陽子線、重粒子線などの放射線治療が、肝がんの治療に適応されることもあります。化学療法は、肝切除や穿刺療法、肝動脈塞栓術などの治療で効果が得られない場合などに行われることがありますが、治療効果があまり高くないのが現状です。