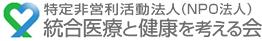Menu
悪性黒色腫(メラノーマ)
【1】悪性黒色腫とは
1.悪性黒色腫の発生
皮膚に発生する皮膚がん(皮膚悪性腫瘍)はいろいろな種類がありますが、悪性黒色腫はその中のひとつで、最も悪性度が高いと恐れられています。皮膚の色と関係するメラニン色素を産生する皮膚の細胞をメラノサイトと呼び、悪性黒色腫はこのメラノサイト、あるいは母斑細胞(ぼはんさいぼう:ほくろの細胞)が悪性化した腫瘍と考えられ、単に黒色腫またはメラノーマと呼ばれることもあります。
2.悪性黒色腫の統計
悪性黒色腫は悪性度が非常に高いがんです。 発生部位は足底(足のうら)が最も多く、体幹、顔面、爪が続きます。どこの皮膚にも発生しますが、ふだんあまり気にしない足底に最も多いことは注意すべき点です。その他、悪性黒色腫は皮膚だけでなく、頻度はあまり多くありませんが粘膜にも発生することがあります。
3.悪性黒色腫の原因と予防
悪性黒色腫の発生原因は不明ですが、白色人種の発生率が有色人種よりも数倍高く、紫外線の強い地域に住む白色人種の発生率がさらに高いという報告もあり、紫外線が関係している可能性があります。また、白色人種では家族内で発生したり、数ヶ所の皮膚に多発したりする家系が報告されており、遺伝的に悪性黒色腫が発生しやすい家系があると考えられていますが、わが国では今のところそのような家系は明らかではありません。わが国では、足底や爪部などふだん慢性的に刺激を受けやすい部位、あるいは衣類などですれる部位や外傷を受けた部位などに発生が多くみられることより、外的刺激も危険因子のひとつと考えられています。
私たちは白色人種に比べて紫外線に抵抗力がありますが、過度な日焼けは避けたほうが無難であると思われます。また、ほくろと思われるしみに対して、自分で針を刺したり、焼いたりしてとろうとすることは絶対によくありません。ほくろを刺激しないように心がけるべきです。さらに、成人後出現したほくろが次第に大きくなったり、色が濃くなったりしてきた場合は、早めにお近くの皮膚科を受診して下さい。
4.悪性黒色腫の早期発見
ほくろの細胞(母斑細胞)またはメラノサイトが悪性化し、悪性黒色腫になる一歩手前の状態が存在し、悪性黒色腫前駆症と呼ばれています。この前駆症の状態ないしは早期の悪性黒色腫の状態で発見することが最も重要です。
悪性黒色腫の治療は早期に発見し、早期に手術によって大きく完全に切除することが第一です。皮膚は身体の表面にありますので、注意すれば自分もしくは家族により悪性黒色腫を早期に発見することが可能です。しかしながら、早期の場合には、普通のほくろと悪性黒色腫を区別することは非常に難しく、少しでもおかしいと思われるほくろがあった場合は自己判断せずに、まず皮膚科医師を受診することが、早期発見、早期治療につながります。特に生まれつきではなく、途中からできたほくろで急速に大きくなり、直径5mm以上になったものは要注意です。悪性黒色腫を放置すると、早期に所属リンパ節(最初に発生した部位から一番近いリンパ節)に転移することが多く、さらには肺、肝臓、脳など重要な臓器に転移してしまいます。悪性黒色腫は全身どこの臓器にも転移します。進行した悪性黒色腫に対しては、外科療法の他、抗がん剤による化学療法、リンパ球などを使った免疫療法、および放射線療法などいろいろな手段を組み合わせた治療(集学的治療)が行われます。
【2】悪性黒色腫の皮膚症状
悪性黒色腫の臨床症状は非常に複雑で多彩ですが、大きく4つのグループ(病型)に分けられています。まず、悪性黒色腫の前駆症および早期の症状について説明し、次に悪性黒色腫の4つの病型について説明します。
1.悪性黒色腫の前駆症および早期の症状
比較的短期間(約1~2年以内)に次のような変化があれば、要注意です。
-
(1)色の変化
一般に薄い褐色が濃い黒色に変化する場合が多くあります。また、色調に濃淡が生じて茶褐色、青色などが相混じったり、一部色が抜けてまだらになることもあります。
-
(2)大きさの変化
1~2年以内の経過で、直径2~3mm程度の色素斑が5~6mm以上になった時は注意すべきです。短期間に目立って大きくなるものは要注意です。
-
(3)形の変化
色素斑の辺縁が、ぎざぎざに不整になったり、しみ出しが出現したりすることがあります。色素斑の一部に硬結や腫瘤(しゅりゅう:かたまりのできもの)が出現した場合は要注意です。
-
(4)かたさの変化
一般に、ほくろは均一なかたさをしていますが、その一部または全体がかたくなってくることがあります。
-
(5)爪の変化
爪にできる場合は他の皮膚と違い、爪に黒褐色の色素線条(縦のすじ)が出現し、半年~1年くらいの短期間に色調が濃くなって、すじの幅が拡大してきます。進行すると爪が割れたり、色素のしみ出しが出現することがあります。
2.悪性黒色腫の4病型とその症状
-
(1)悪性黒子型黒色腫
顔面、頸部、手背(しゅはい)など日光に照射されやすい露出部位に発生します。はじめ褐色~黒褐色の色素斑が出現し、この時は悪性黒子と呼ばれる前駆症の状態であり、経過はゆるやかで数年以上存在することがあります。やがて色調は濃黒色を混じ、次第に拡大し、さらに一部に硬結や腫瘤が出現してきて悪性黒色腫になります。一般に60歳以上の高齢者に発生することが多く、ゆるやかに成長するため、治療により治癒する確率が4病型のうちで最も高いといわれています。最近の全国アンケート集計では、この病型の占める割合は9.5%で、4病型のうちで最も少ないのですが、以前に比べ割合は増加傾向にあります。
-
(2)表在拡大型黒色腫
ほくろの細胞(母斑細胞)から発生すると考えられ、前駆症の状態を経て、全身どこにでも発生します。はじめわずかに隆起した色素斑からはじまることが多く、やがて表面が隆起し、表面および辺縁ともに不整となり、色調も褐色~黒褐色より一部濃黒色となり濃淡相混ずることが多くなります。一般に50歳代に発生することが最も多いのですが、子供~高齢者まで広い年齢層で発生します。比較的腫瘍の成長はゆるやかですが、悪性黒子型黒色腫より治癒する確率が低くなっています。最近の全国アンケート集計では、この病型の占める割合は15.7%で、4病型のうちで2番目に少ないのですが、この病型も以前に比べ割合は増加傾向にあります。
-
(3)結節型黒色腫
全身どこにでも発生し、ほとんど前駆症の状態をあらわさないで、はじめから急速に成長することが多い病型です。症状としては、はじめから立体構造をしていることが多く、山なり、半球状、有茎状(ゆうけいじょう:くびれのある結節状)などの形を示します。色調ははじめ褐色~黒褐色ですが、だんだんと全体的に濃黒色となったり、あるいは濃淡相混ずることになります。いろいろな年齢層に発生しますが、一般に40~50歳代に最も多く発生します。腫瘍の成長は速く、早期に深部に進行したり、転移したりすることが多く、最も悪性度が高い病型です。最近の全国アンケート集計におけるこの病型の占める割合は30.0%で、4病型のうちで2番目に多いのですが、この病型は以前に比べ割合はやや減少傾向にあります。
-
(4)末端黒子型黒色腫
わが国で最も多い病型であり、主に足底(足のうら)、手掌(手のひら)、手足の爪部に発生し、そのうちで足底に最も多い病型です。足底および手掌では、はじめ前駆症として褐色~黒褐色の色素斑が出現し、次第に色素斑の中央部を中心として黒色調が強くなり、その中央部に結節や腫瘤ができたり、潰瘍(かいよう)ができたりしてきます。爪部では、はじめ前駆症として爪に黒褐色の色素線条(縦のすじ)が出現し、半年~1年くらいの短期間に色調が濃くなって、すじの幅が拡大し、爪全体に広がってきます。次に爪が割れたり、褐色~黒褐色の色素のしみ出しが爪の周辺の皮膚に出現したりすることがあります。さらに進行すると爪がとれ、爪の部位に結節や腫瘤ができたり、潰瘍ができたりします。いろいろな年齢層に発生しますが、一般に40~50歳代に最も多く発生します。腫瘍の成長は結節型黒色腫よりゆるやかで、前駆症や早期の状態で発見されることが可能であり、一般に結節型黒色腫より治癒する確率が高く、表在拡大型黒色腫より低いと考えられています。最近の全国アンケート集計では、この病型の占める割合は44.8%で、4病型のうち最も多く、以前に比べ割合はあまり変わっていません。
【3】診断
臨床症状の総合的な診断によることが多いのですが、診断の確定には腫瘍の標本の検査(病理組織検査)が必要です。しかし、わが国では悪性黒色腫の一部に直接メスを入れて病理組織検査(皮膚生検)を行うと、転移を誘発する可能性もあると考えられていて、やむをえない場合を除いて行われません。 臨床症状により診断が困難な場合は、手術で腫瘍全体を切除し、手術中にすぐできる病理組織検査(迅速組織検査)を行います。悪性と診断された場合には、さらに大きく切除することになります。腫瘍の表面がじくじくした状態の時は、その部分にスライドガラスを押し当てて採取した細胞の検査(細胞診検査)が診断の助けになったり、血液中の腫瘍マーカーと呼ばれる物質(悪性黒色腫の場合、5-S-シスチニールドーパという物質)の検査値が参考になったりすることもあります。リンパ節や内臓のほうへの転移を調べるためには、X線、CT、超音波、シンチグラム、MRI、PETなどの画像診断と呼ばれる検査が行われます。
【4】治療
1.外科療法
悪性黒色腫は他のがんと同様に早期発見、早期治療が最も重要なことです。 そして、早期発見時における治療の最大のポイントは手術による外科療法です。悪性黒色腫は、初発病巣の周囲に皮膚転移(衛星病巣)が数ヶ所発生することが多いという特徴をもっており、初発病巣のみを小切除して放置した場合、その周囲にかなり高い確率で腫瘍が再発します。また、わが国では、悪性黒色腫の一部に直接メスを入れて病理組織検査を行うと、転移を誘発することがあると考えられています。したがって最初の治療において、初発病巣辺縁より数cm大きい範囲で広範囲に切除手術を行うことが原則です。また、外来で腫瘍のみを小切除した後、診断確定された場合は、できるだけ早期に、広範囲に再手術したほうがよいとされています。
2.化学療法
抗がん剤による治療を化学療法と呼び、悪性黒色腫の場合は静脈内注射薬を数種類組み合わせて行われます。手術後、検査でとらえられないような微小な腫瘍細胞を殺して再発、転移を予防するために行われたり、内臓やリンパ節の転移巣を消滅させたりするために行われます。一般に1コースあたり、連日5日間抗がん剤の点滴静脈内注射が行われ、その後4~6週間休薬します。一般的に数コース繰り返し行われますが、何コース行われるかは病気の進行程度や治療効果に関係してきます。
3.放射線療法
一般に行われる放射線では効果が上がらないことが多く、速中性子線や重粒子線といわれる特別な放射線では効果を示すことがあります。しかし、このような治療はごく限られた施設でしか行うことができません。また、放射線治療に温熱療法(腫瘍細胞を42℃以上に暖めて殺す治療)を併用すると皮膚転移にかなり効果があります。
4.免疫療法
自分の身体の免疫という力を強力にすることによる治療を免疫療法といい、悪性黒色腫はこの免疫療法の効果が期待される腫瘍といわれています。しかし、いろいろな免疫力を上げる薬の効果が検討されていますが、正式に認可を受けた薬はありません。現在、免疫を担当する自分のリンパ球を薬を使って体外で増やし、再び自分の体内にもどす免疫療法を行っている施設もあります。 その他、インターフェロン(ヒトがつくり出す生理活性物質で、一部のがんやウイルスの増殖を抑制する作用が認められています)が皮膚転移に効果があることが認められています。悪性黒色腫の場合、皮膚転移以外に転移がみられない場合があり、その際直接皮膚転移に注射されたり、他の治療法と併用して行われたりします。
【5】病期(ステージ)
がんの進行程度を病期といい、悪性黒色腫は次のようにI~IV期の4つに分類されています。
-
I期
初発部位にのみ腫瘍を認め、転移を認めないもので、初発部位における腫瘍自体の厚さが1mm以下のもの、または厚さが1mmを超えていても腫瘍表面の潰瘍がなくて2mm以下のもの。
-
II期
初発部位にのみ腫瘍を認め、転移を認めないもので、初発部位における腫瘍自体の厚さが1mmを超えていて2mm以下であり、潰瘍を伴うもの、または潰瘍のあるなしにかかわらず、2mmを超えるもの。この中でも特に厚さ4mmを超えるものは要注意。
-
III期
次のいずれかが認められる場合
所属リンパ節(初発部位から最も近いリンパ節)に転移を認めるもの。 もしくは初発部位の周囲(衛星病巣と呼ぶ)、または初発部位から所属リンパ節までの間に皮膚転移や皮下転移を認めるもの。 -
IV期
所属リンパ節を越えた領域に皮膚転移、皮下転移、リンパ節転移を認めるもの、または内臓に転移を認めるもの。
【6】各病期(ステージ)別治療
-
I期
初発部位の腫瘍辺縁より1~2cm離して広汎切除手術が行われます。しかし、指などの場合、切断手術になることもあり、また部位によっては植皮手術を行う場合もあります。
-
II期
初発部位の腫瘍辺縁より2~3cm離して広汎切除手術を行い、しばしば植皮手術が行われます。予防的に所属リンパ節の郭清手術(リンパ節をすべてとりさること)、センチネルリンパ節生検が行われます。また、腫瘍の再発や転移を予防するために抗がん剤治療や、インターフェロンによる免疫療法が行われます。
-
III期
初発部位の腫瘍辺縁より2~3cm離して広汎切除手術を行い、所属リンパ節の郭清手術が行われます。皮膚転移や皮下転移に対しては大きめに切除したり、インターフェロンを注射したり、放射線治療を行ったりします。また、腫瘍の再発や転移を予防するために抗がん剤治療が行われます。治療後、腫瘍の再発や転移が発生する確率が高く、厳重に定期検査を行う必要があります。
-
IV期
病状により異なりますが、外科療法の他、抗がん剤による化学療法、リンパ球などを使った免疫療法、および放射線療法などいろいろな手段を組み合わせた治療(集学的治療)が行われます。
例えば、肺や脳転移に対して手術が可能な場合、積極的に切除を行い、術後強い抗がん剤治療が繰り返し行われます。しかしながら、手術が可能な場合は少なく、一般に強い抗がん剤治療が主体になります。皮膚転移や皮下転移に対してはIII期と同様な治療が行われ、やはり強い抗がん剤治療が繰り返し行われます。 現在のところ集学的治療を行い、寿命の延長ができても、治癒することは非常に難しいといえます。最近、新しい免疫療法による治療が試みられようとしています。
【7】治療の副作用
1.外科療法
病変が皮膚の場合、美容的な問題が生じることがあります。切断手術を行った場合、患肢のしびれや痛みが残ることがあります。所属リンパ節をとった場合、患肢のはれ(浮腫)やしびれが残ることがあります。
2.化学療法
抗がん剤はがん細胞以外の正常細胞にも影響を与えるため、いろいろな副作用を生じます。その症状や程度は抗がん剤の種類や量、個人差などによって異なります。一般的には、白血球減少、血小板減少、貧血、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、手足のしびれ、肝機能障害、腎機能障害、脱毛、倦怠感などです。抗がん剤を投与する場合は、このような副作用を軽減させるための処置が同時に行われます。
3.放射線療法
放射線照射部に一致して皮膚炎をおこすことがありますが、かゆみ止めや痛み止めの薬の内服や軟こうの外用により症状は軽減し、照射終了後時間とともに軽快します。
4.インターフェロン治療
発熱することがありますが、解熱剤により下げることができます。白血球減少、食欲不振、肝機能障害などが軽度生じることがあります。