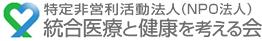Menu
陰茎がん
【1】陰茎がんとは
陰茎がんは、陰茎に発生する極めてまれながんで、人口10万人当たりの死亡率は0.1程度です。年齢別にみた罹患(りかん)率は、60歳から80歳で高く、65歳から70歳にピークがあります。 扁平上皮がんがほとんどであり(95%以上)、大部分の症例が比較的おとなしい高分化型です。 陰茎がんは、包茎、亀頭包皮炎、生殖器の不衛生がリスク要因ではないかと考えられています。梅毒や尖圭(せんけい)コンジロームなどの性感染症や、性的パートナーが多いこと、また、陰茎がんの男性を夫に持つ女性では子宮頸がんのリスクが高くなることから、ヒューマン・パピローマ・ウイルス感染もリスク要因の候補に挙げられています。 その他、光化学療法PUVA(ソラレン8-methoxypsoralen+UV-A)を受けている乾癬(かんせん)患者でリスクの上昇が報告されていて、紫外線もリスク要因となる可能性が指摘されています。
【2】症状
陰茎がんは、痛みを伴わないのが普通です。がんはまず陰茎の皮膚から発生しますが、カリフラワー状に外方に発育するものや、湿疹様の発赤から次第に深部に浸潤していくものがあります。進行すると海綿体や尿道にも浸潤(しんじゅん:がんが周囲に広がること)し、排尿が困難になることがあります。がんが大きくなると潰瘍(かいよう)を形成したり、がんが崩れて出血することがあります。また、陰茎がんは鼠径部(そけいぶ)と呼ばれる大腿のつけ根の部分のリンパ節に転移しやすいので、進行すると鼠径部のリンパ節をかたく触れるようになります。これがさらに大きくなると、リンパの流れが悪くなって、足のむくみが出現することがあります。医師の診察を受けるのが遅れ、がんの早期発見の機会を逃して手遅れとなることが多いので、自覚症状があったらすぐに診察を受けることが大切です。
【3】診断
肉眼的に見て診断がつく場合がほとんどです。 しかし、確定診断のためには、局部麻酔をして病変部の一部を切除して顕微鏡で検査する(生検)か、病変部をこすってはがれた細胞を顕微鏡で調べる検査(細胞診)が必要です。陰茎によくみられる他の疾患、特に尖圭コンジローマという病気がありますが、これが大きくなると陰茎がんとの鑑別がやや難しくなるので、これらの検査が必要です。 その他に最も転移しやすい鼠径部のリンパ節の触診も重要です。 がんであることがわかったら他のがんと同様、胸部X線撮影、腹部のCT、エコーなどで他臓器に転移がないかを確かめる必要があります。
【4】病期(ステ-ジ)
陰茎がんは以下の病期に分類されています。
-
I期
がんが亀頭部のみ、あるいは陰茎の皮膚のみに限局している。
-
II期
がんが亀頭部を越えて広がっているが、転移がない。
-
III期
鼠径部のリンパ節に転移がある。
-
IV期
鼠径部を越えて骨盤内のリンパ節に転移がある、あるいは他の臓器に転移がある。
【5】治療
陰茎がんの治療の主体は外科療法あるいは、放射線療法です。
1.外科療法
手術の適応があるのは、I、II、III期です。 手術は全身麻酔をして病変部の切断と、鼠径部のリンパ節を摘除する操作(リンパ節郭清:りんぱせつかくせい)を同時に行います。場合によっては、さらに骨盤部のリンパ節も摘除することがあります。病変部から最低2cmは離して切断するため、当然陰茎は短くなります。この場合、術後、立位での排尿は可能な場合もあります。 また、陰茎を根本から切断し、尿の出口を会陰部にもってくることもあります。術後は鼠径部のリンパ節郭清の影響で、足がむくみやすくなる傾向があります。手術後は陰茎が小さくなり排尿は座位で行うことになります。そのままでは性交も難しいので、形成外科的な手法で人工的な陰茎を形成する手術を行うこともあります。
2.放射線療法
放射線療法の対象になるのは、比較的初期のがんに限られます。陰茎のかたちをある程度保てることが利点ではありますが、治癒する確率は手術に比べると落ちます。ただし、I期では手術と比較し、成績はほとんどかわりません。治療後に陰茎の変形や、尿道の狭窄(きょうさく)をきたすことがあります。転移があると疼痛などの症状があらわれるため、その対策として放射線療法が選択されることがあります。
3.化学療法
転移が認められるような陰茎がんは、抗がん剤治療の対象になり、リンパ節転移を有する症例ではリンパ節郭清と併用して行うこともあります。シスプラチン、メソトレキセート、ブレオマイシンの併用療法がよく用いられます。また、II期、III期において、手術の前後に化学療法を併用し、手術成績の向上をはかる試みもされています。